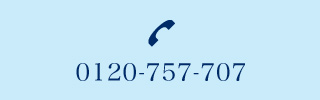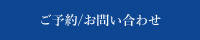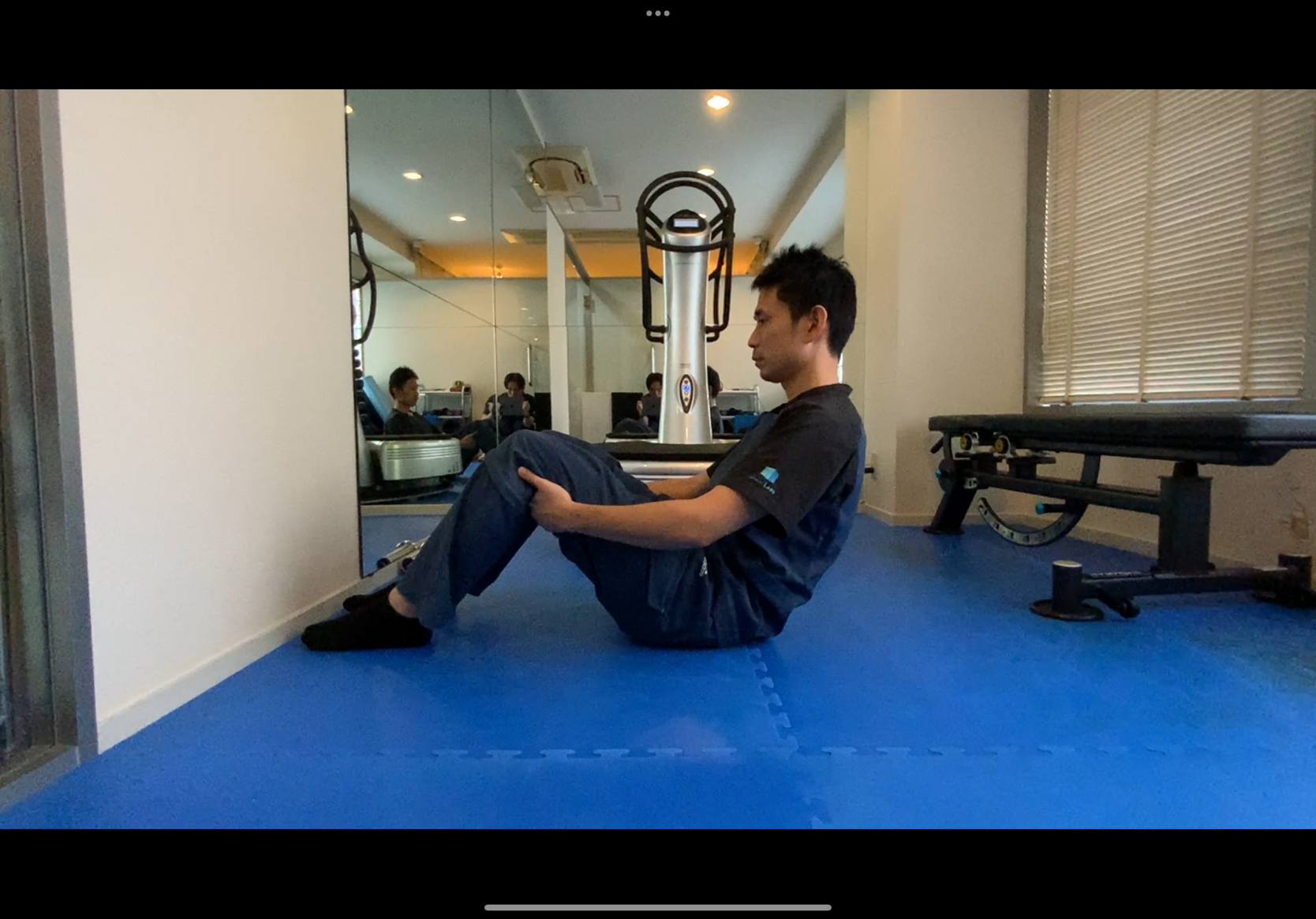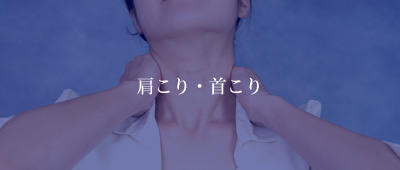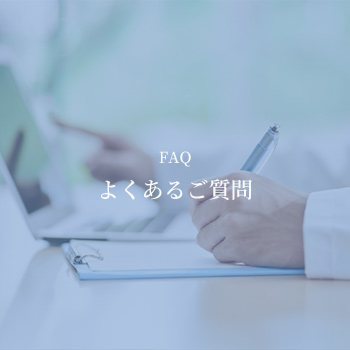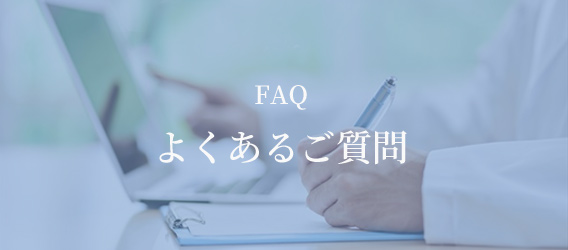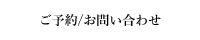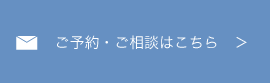前回の記事では、胸の背骨(胸椎)では「ひねる動き(回旋)」と「横に倒れる動き(側屈)」が、構造上セットで起こりやすいという特徴についてお話ししました。
今回はその続きとして、この胸椎の動きの左右差が、どのように首や肩の左右差、そして首の痛みにつながっていくのかについてお伝えしていきます。
「なぜか首の痛みはいつも同じ側に出る」「肩の高さが左右で違う気がする」
そんな方々にとって、体のつながりを見直すヒントになれば幸いです。
胸椎の側屈・回旋の左右差が肩の高さを変える
肩の高さに左右差があると、多くの方は「肩そのもの」や「肩甲骨」に原因があると考えがちです。
実際、評価の際にも肩甲骨の位置や動きを指標にすることは多いです。
しかし、肩の高さの左右差は、必ずしも肩甲骨だけで決まっているわけではありません。
体の中心にある背骨、特に胸椎が側屈や回旋している結果として、肩の高さに差が生じているケースもあります。
肩の高さの左右差は肩甲骨で見る?
肩の高さに左右差がある場合、まず注目されやすいのが肩甲骨の位置です。
「片側の肩甲骨が上がっている」「下がっている」といった見方は、実際の評価でもよく用いられます。
確かに、肩甲骨の位置や動きは、肩の高さに大きく関係しています。
そのため、肩の左右差を見るうえで、肩甲骨を指標にすること自体はとても大切な視点です。
ただし、ここで一つ知っておいていただきたいのは、肩甲骨の高さは「結果」として現れていることも多いという点です。
胸椎の傾きが、肩の高さの左右差を作る可能性について
肩甲骨の高さが左右で違って見える背景には、その土台となる背骨の傾きが関係している場合があります。
特に影響しやすいのが、胸の背骨(胸椎)の横への傾き、つまり側屈です。
たとえば、胸椎が右に少し傾いた状態を想像してみてください。
体幹全体が右に倒れるような形になるため、右肩は相対的に下がり、左肩は高く見えやすくなります。
この場合、肩甲骨そのものに大きな問題がなくても、背骨の傾きによって、肩の高さに左右差が生まれていることになります。
肩甲骨だけを整えても変わらない原因は?
肩の左右差に対して、肩甲骨周りの調整やエクササイズを行っても、思ったように変化が出ないケースがあります。
その理由のひとつが、肩甲骨の位置を作っている「土台=背骨」が変わっていないことです。
胸椎が側屈や回旋したままの状態では、その上に乗っている肩甲骨だけを整えようとしても、元の傾きに引っ張られて、すぐに戻ってしまうことがあります。
つまり、肩の高さの左右差を見ていく際には、肩甲骨そのものだけでなく、胸椎の傾きや回旋といった体幹の状態にも目を向けることが大切です。
胸椎の側屈・回旋の左右差が首の筋肉に与える影響
肩の高さに左右差が生まれる背景に、胸椎の側屈や回旋が関係していることをお伝えしました。
実は、この状態は肩だけでなく、「首」にも大きな影響を与えます。
首は、胸椎の上に積み重なるように位置しています。
そのため、胸椎に傾きやねじれがある状態が続くと、首もその影響を受けやすくなります。
胸椎の傾きがあると、首は「真っすぐ」を保ちにくい
胸椎に傾きやねじれがある状態では、首は左右で条件の違う状態から動くことになります。
それでも私たちは、
- ・視線を正面に保つ
- ・頭の位置を安定させる
といった調整を、無意識のうちに行いながら生活をしています。
その結果、見た目上は頭がまっすぐに保たれていても、首の筋肉の使われ方には左右差が生じやすくなります。
このような状態が続くことで、違和感や痛みがいつも同じ側に出やすくなっていきます。
首の筋肉に生じる「伸ばされる側」と「縮む側」
胸椎の側屈・回旋によって体幹が傾いていると、首では次のようなことが起こりやすくなります。
- ・片側の筋肉は、引き伸ばされ続ける
- ・反対側の筋肉は、縮み続けた状態になる
引き伸ばされ続けている筋肉には、ゴムが引き伸ばされ続けるような「伸張ストレス」がかかります。
一方で、縮み続ける筋肉には押しつぶされるような「圧迫ストレス」がかかります。
どちらの状態も首にとっては負担となり、緊張や違和感が抜けにくくなります。
この状態が続くことで、
- ・片側だけ首が痛くなる
- ・いつも同じ側の首が張る
- ・振り向く方向によって痛みが出る
といった、左右差のある首の症状につながっていきます。
首そのものが悪いとは限らない
首に痛みや違和感があると、「首が悪いのではないか」と考えやすくなります。
実際、触ってみると張りが強かったり、動かすと痛みが出たりするため、そう感じるのは自然なことです。
ただ、ここまで見てきたように、肩の高さや首の筋肉の左右差は、胸椎の動きの影響を受けて生じている場合もあります。
このような状態では、首の筋肉を一時的に緩めても、体の土台となる胸椎の傾きやねじれが残っていると、首には再び同じ負担がかかりやすくなります。
つまり、首の痛みや左右差は首そのものだけの問題ではなく、体全体の動きの結果として現れている可能性があるという視点を持つことが大切です。
まとめ
今回は、首の痛みに左右差が出る理由を、胸椎の動きという視点からお伝えしてきました。
胸椎の側屈や回旋に左右差があると、体幹がわずかに傾き、その影響が肩の高さや首の筋肉の使われ方に現れてきます。
首は胸椎の上に積み重なっているため、見た目では真っすぐに保っていても、左右では違う負担がかかっている可能性があります.
首に違和感や痛みがあると、「首が悪いのではないか?」と感じるのは自然なことです。
ただ、首だけを整えても症状を繰り返してしまう場合、背景に胸椎の傾きや体の使い方が関係している可能性も考えられます。
体は一部分だけで成り立っているわけではなく、背骨を通して全身がつながっています。
首の不調をきっかけに、体の中心である背骨、特に胸椎の動きにも目を向けてみることで、これまで気がつかなかった改善のヒントが見えてくるかもしれません。

執筆者:進藤 孝大
Takahiro Shindo
湘南医療福祉専門学校 アスレティックトレーナー科卒業
東京衛生学園専門学校 東洋医療総合学科卒業
鍼師・灸師・按摩マッサージ指圧師
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)
A-Yoga Movement coach
目の前にいる人の体のお悩み解決に全力を尽くす。
その想いだけで活動してまいりました。
スポーツトレーナーとして培ってきたノウハウと経験を活かして、
運動療法と鍼灸マッサージを組み合わせた治療を提案。
ご自身に合った適切なケア方法等、皆様のお悩み解決に向けて徹底サポートを行います。