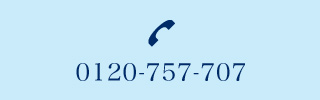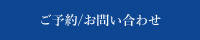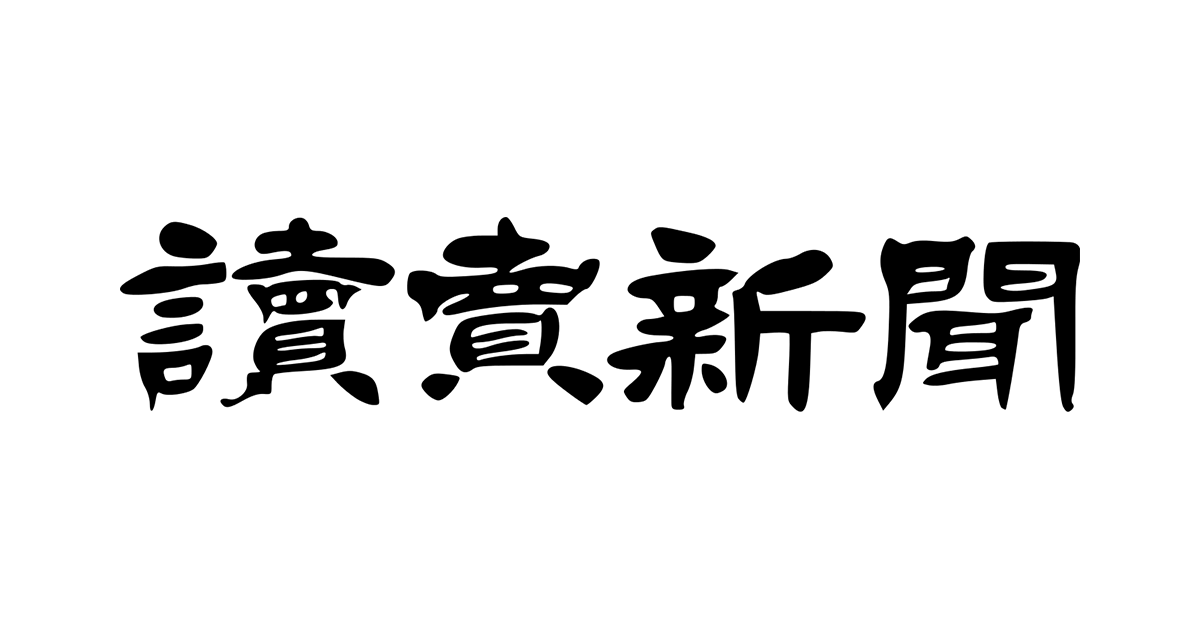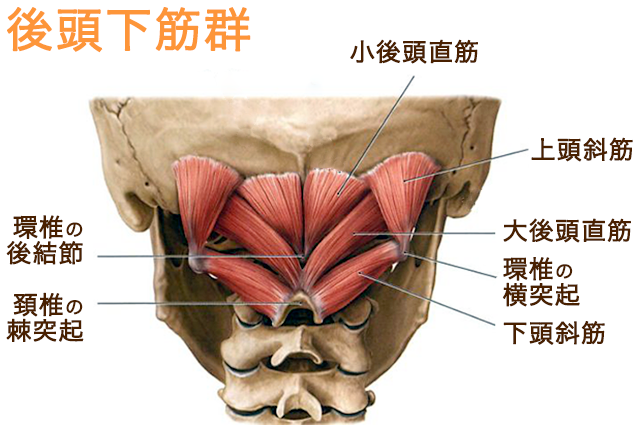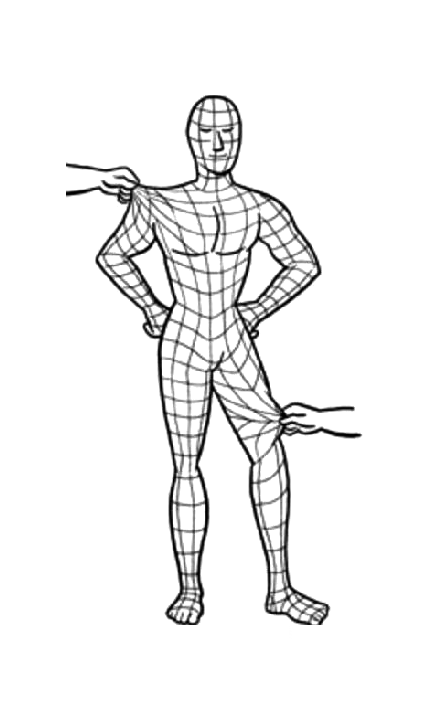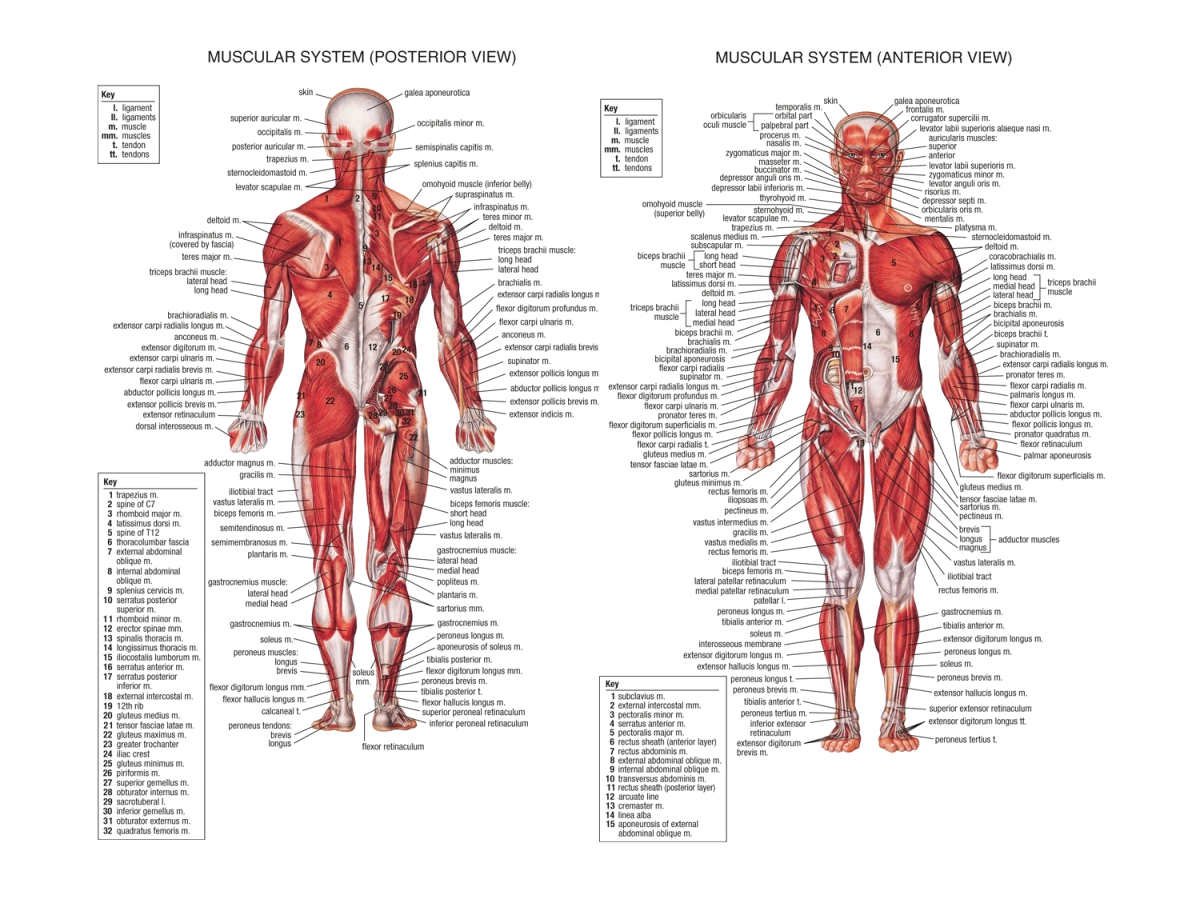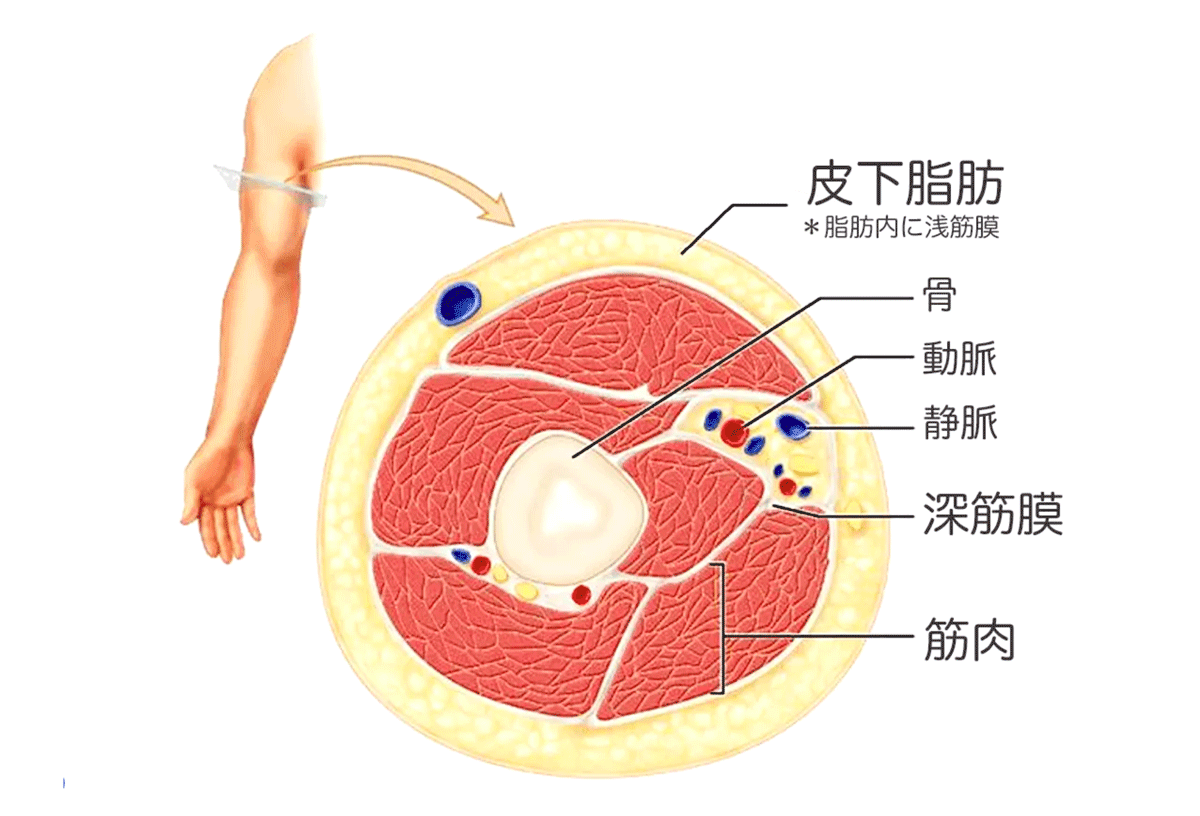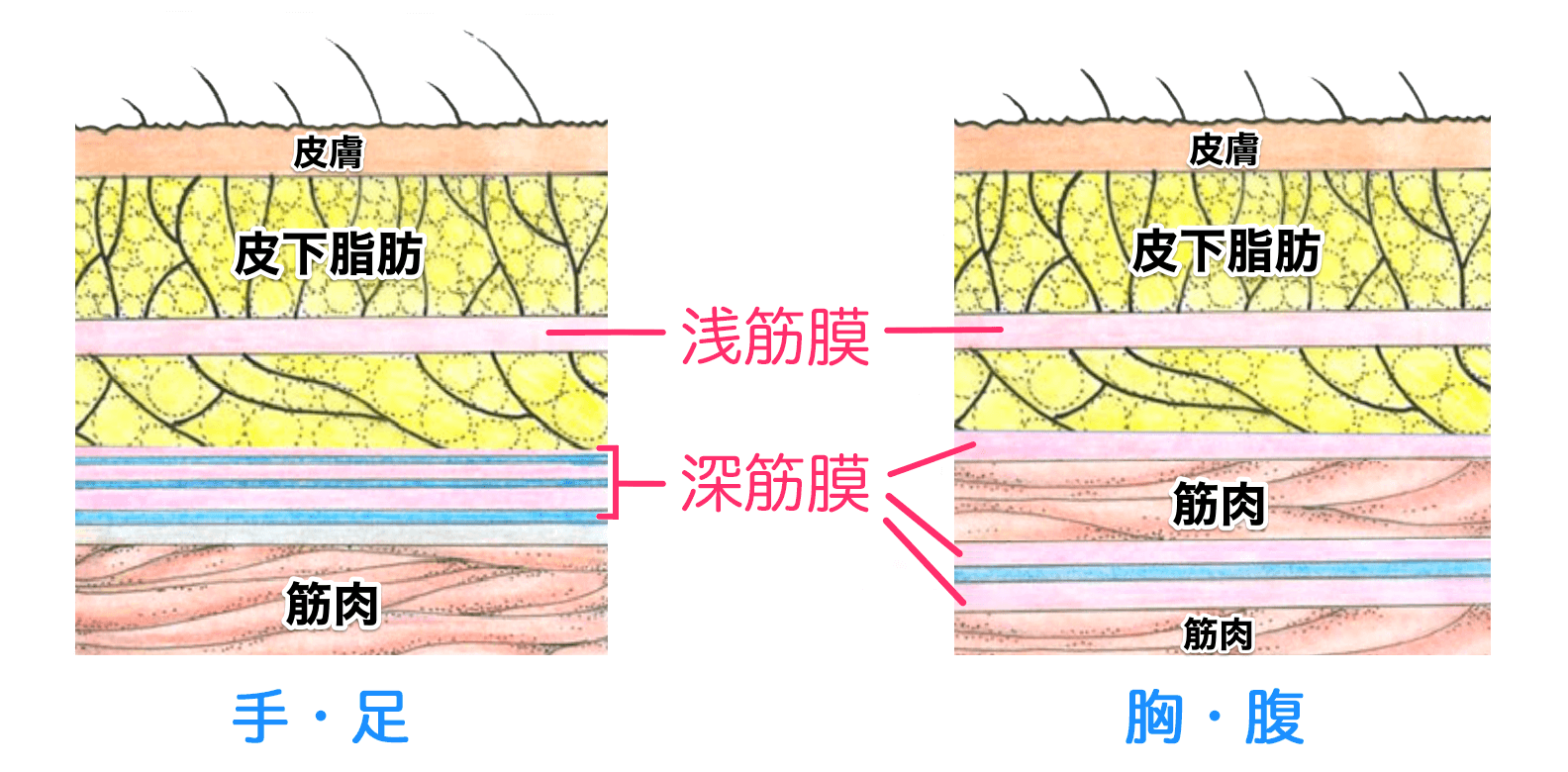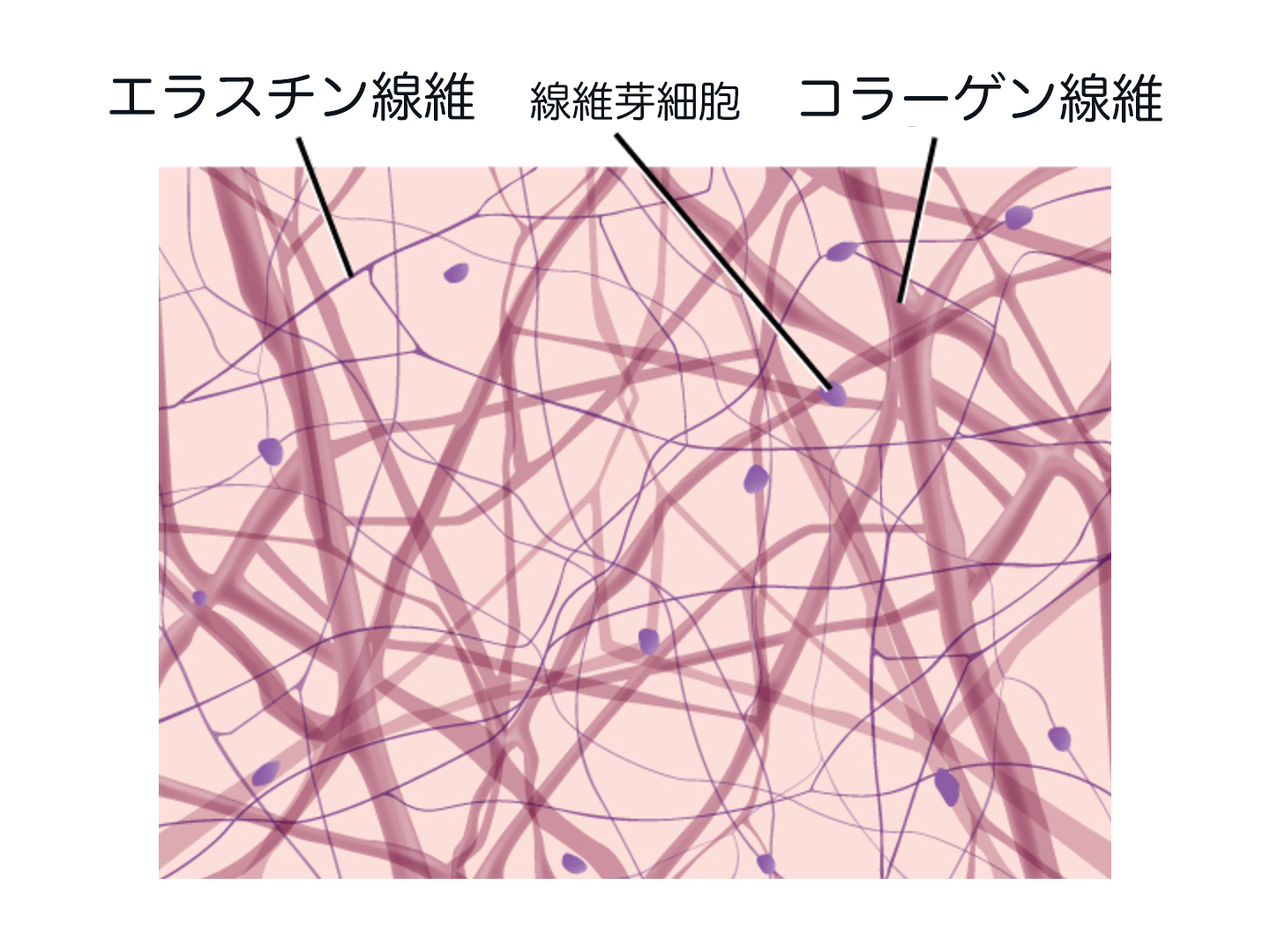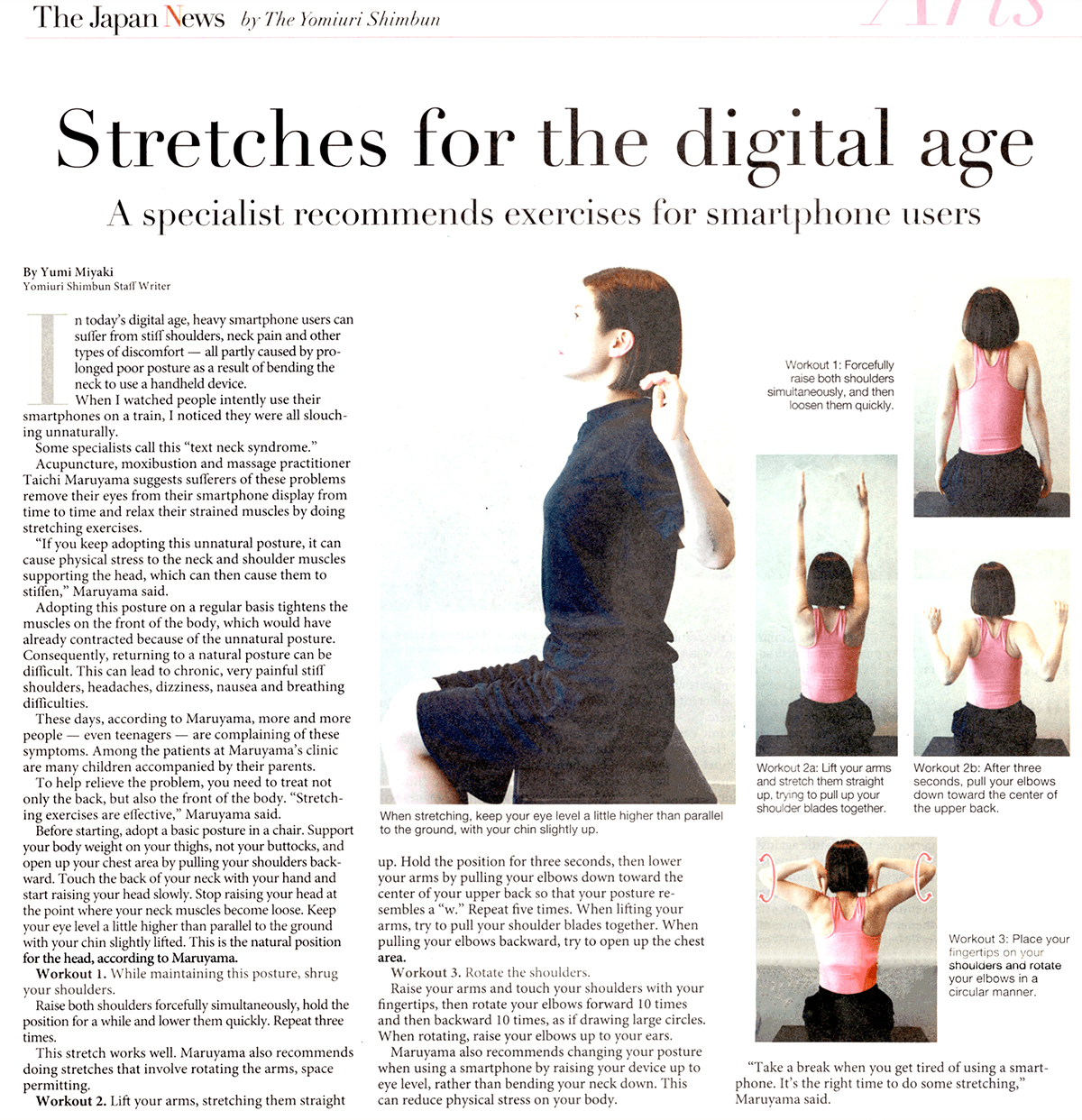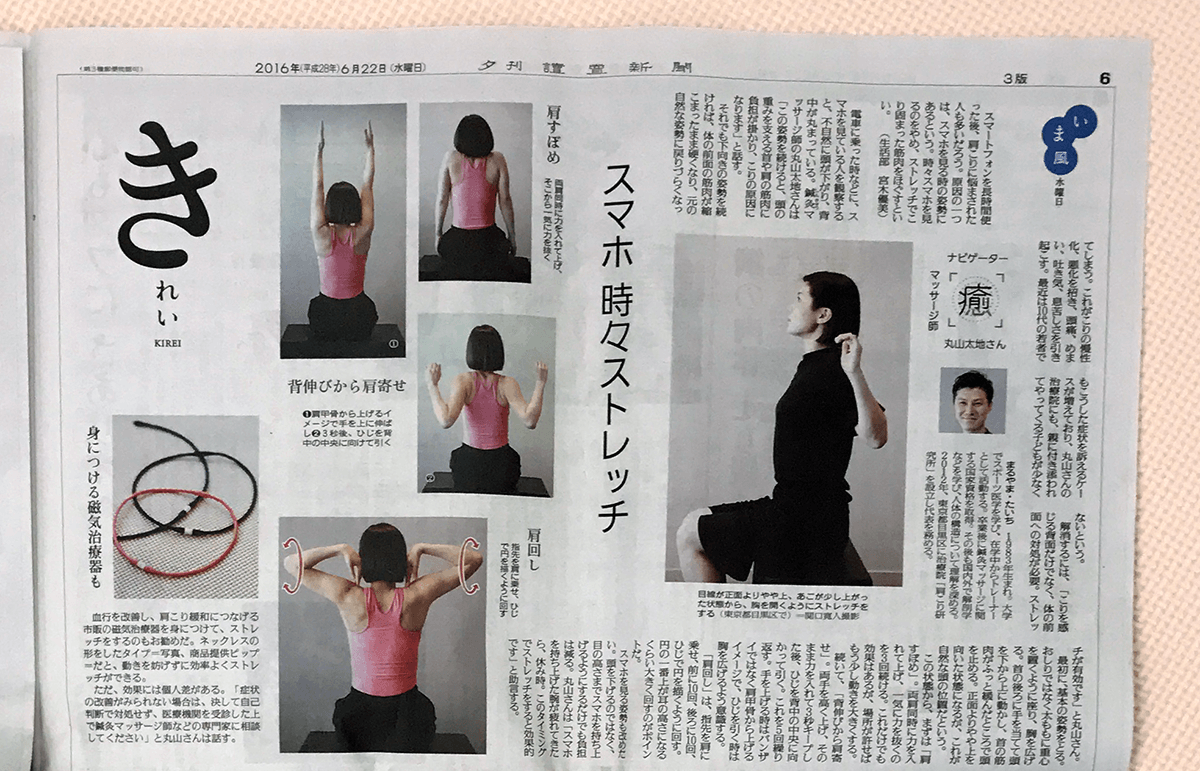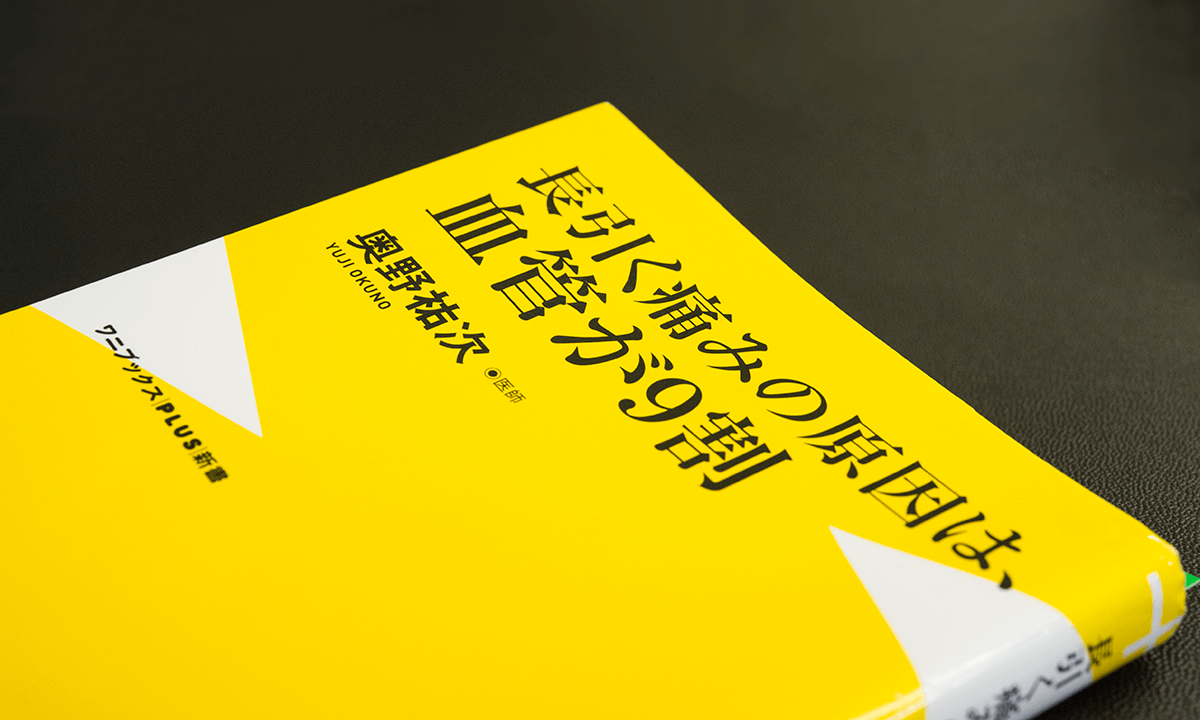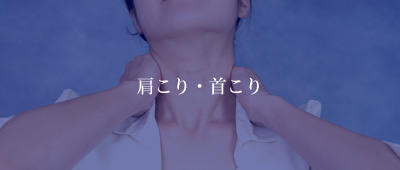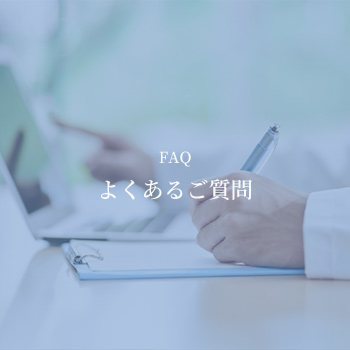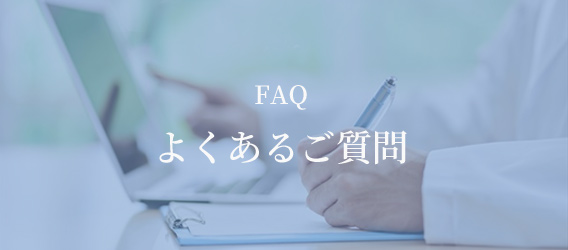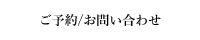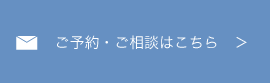肩こりラボで行っている施術の紹介記事が「医道の日本 11月号」に掲載されました。
先月「医道の日本 10月号」では肩こりラボ開設にあたっての経緯や理念について取り上げていただきました。今号では具体的な施術の中身についてです。
施術の中身と聞くと「具体的にどんな方法?」「どんな特殊技術をやっているのだろう?」とお考えになるかもしれません。月刊「医道の日本」は鍼灸に携わる人・将来携わる人が読む専門誌です。一般の方向けの雑誌ではなく専門誌において特に私たち肩こりラボとして訴えたかったことは「治すために必要なこと」です。こんなすごいコトをしている!!といったテクニック自慢ではございません。
その理由は、鍼灸に携わっている方・将来携わるであろう方々に「肩こりラボというところは、本気で肩こり患者をなくすことを目指している鍼灸院なんだ」と認識していただき、そしてkatakori LABSの「志」を知っていただいて、そこから広がる可能性に期待しているからです。
有資格者も含めて一般的には、知識技術があり、特に特殊技術を持ち合わせたいわゆる「ゴッドハンド」が優れたセラピストであるという認識をされる場合があります。しかし当院はそのように考えておりません。
もちろん、施術を行うにあたり一定以上の知識や技術は必要なことですし、患者さんの苦痛を一刻も早く取り除くために極力即効性がある理学療法を追究することはセラピストとして当然の考えです。しかしそれがいき過ぎて、知識技術偏重の思考に偏ってしまうと、セラピストとして大切な包括的で客観的な視点が弱まり「患者さんを診る」ということを見失ってしまうことになりかねないと私どもは危惧しています。
katakori LABSは「一人でも多くの方を、より高い確率で、かつ最短で治すこと」を命題と掲げています。
肩こりラボには「ゴッドハンド」はいません。
当院の施術者はそれぞれ性格・タイプがバラバラなのですが、個々によって施術の方法、方針が異なることはなく、「治す」という共通の目的に向かって皆同じ方向を向き、共通の思考、技術・方針のもと患者さんと向き合います。神がかった特殊技術は用いずとも、基本を忠実に行い貫くことで一定の成果をあげることができています。
その理由は、
- 疾患ではなく患者さんを診るに徹すること
- 見立て(専門用語では評価という)と計画に注力していること
- 問診などの患者さんとの意志疎通、コミュニケーションを大切にしていること
であると解釈しています。
セラピストであれば、知識技術をアップデートし続けていくのは前提で、それ以外の部分に意識を向けています。
私たちが考えるセラピストとして大切なこと
現在の鍼灸業界は全てではないにせよ、その多くは「施術者が自ら考え、やりたいことをやる」という状況といえるでしょう。
セラピストも人間ですしそれを全否定するつもりはありませんが・・・あくまでも施術を受けるのは患者さんです。施術を受けるのは患者さん、評価するのも患者さんです。
特殊技術を行うことができた、できるようになった喜びというのは施術者本位のものです。それは患者さんにとっての喜びとはまったく異なります。
患者さんは、目的があって通院されるということ、そして治したいという気持ちがあります。受け手である患者さんの心情や、本当の意味で求めることを汲み取り、精査し、伝え、実行するのがセラピストの責務であり資質です。これはすなわち患者さんを診る力ともいえるでしょう。
知識技術偏重思考の結果、この部分がおろそかになってしまっている場合がとても多いのです。結果が求められるのはその後です。
私たちkatakori LABSが期待する可能性
鍼灸業界全体が「治す」という方向へ視点を一斉に向けることができれば、患者さんは多大なメリットを享受することができます。私どもはそれを本当に心から望んでいます。
成果を上げられないからこそ、一時をしのぐことやリラクセーションにはしるなど表面的な部分へ力を注ぐようになってしまい、知識技術偏重の方向へも進んでいってしまっているかもしれません。
それは、施術者の利己的な自己満足の域から出ることはないですし、本当の意味では誰のメリットにもなっていないと思います。
可能ならば、できるかぎり当院の理学療法のノウハウをシェアしたい。
他院との違いをアピールしている以上、矛盾しているように思われるかもしれませんが、可能ならば、できるかぎり当院の理学療法のノウハウをシェアしたいという考えはあります。ただ、どんなに知識技術があっても、そもそもの思考の方向性がずれてしまっていては素材があっても活かすことができません。
高名な大学教授が優れた臨床医かというと必ずしもそうではないように、どんなに知識技術があってもそれが治すということに直結しないことはなんとなくイメージができるのではないでしょうか。
患者さんを治せるようになりたいというモチベーションは高いものの、あらぬ方向へ力を注いでしまっている例が本当に多いため、まずはセラピストとして大切なことがあるのだということ、それが治すためには必要なのだということを強く主張させていただきたいのです。
セラピストとは「治すこと」を生業とする者。
治せなければ、、、セラピストとはいえません。 「治すために必要ないこと」を深く考えて追求していただきたいと願っています。
「治す」という信念のもと、いかなる時もぶれることなく自らの役割を全うすること、そして常に向上心をもって取り組むセラピストはゴッドハンドではなくプロフェッショナルです。
前述したように、業界全体の方向性が変わるということ、そして一人でも多くの「プロフェッショナル」が増えること、「志」あるセラピストが増えることを私どもは本気で望んでいます。これらは患者さんにとってのメリットになると確信しているからです。
「医道の日本」への掲載は、自らのぞんで叶うことではありません。たいへん貴重でありがたい機会をいただき、私たちの信念に基づいて強い想いをこめて取材にのぞませていただきました。
当記事からわずかでもインスピレーションを受けた方がいて、そのような方々からの意志が増え、やがて大きな流れとなること。個の力は小さくとも、それらが集まることで大きな力へと転じ、業界が変わる可能性ともなりうるでしょう。これが私たちの抱く期待です。
katakori LABSは開設3周年
おかげさまで2015年11月1日で開設3周年をむかえることができました。
マンションの一室ベッド一台で気持ちだけは一人前でスタートしましたが、個の力は実に小さく儚いものだと学びました。
多くの方々からの支え、ご指導があったからこそ今があると認識しています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
しかしまだたった三年・・・目標・夢はまだまだ遠く、手が届いておりませんが、ぼんやりしていたものが、はっきりしてきた実感はあります。
緒先輩方が培ってきた歴史は大切に、しかしそれに甘んじることなく常に進化し続けるよう、信念をぶらさずに、温故知新の精神で努めてまいる所存です。
改めて、この大きな機会を与えてくださった「医道の日本」社には心より感謝申し上げます。
医道の日本
TOPページに戻る:肩こりや首こりの治療や解消なら専門情報サイト肩こりラボ

執筆者:丸山 太地
Taichi Maruyama
日本大学文理学部
体育学科卒業 東京医療専門学校 鍼灸マッサージ科卒業
上海中医薬大学医学部 解剖学実習履修
日本大学医学部/千葉大学医学部 解剖学実習履修
鍼師/灸師/按摩マッサージ指圧師
厚生労働省認定 臨床実習指導者
中学高校保健体育教員免許
病院で「異常がない」といわれても「痛み」や「不調」にお悩みの方は少なくありません。
何事にも理由があります。
「なぜ」をひとつひとつ掘り下げて、探り、慢性的な痛み・不調からの解放、そして負のスパイラルから脱するためのお手伝いができたらと考えております。
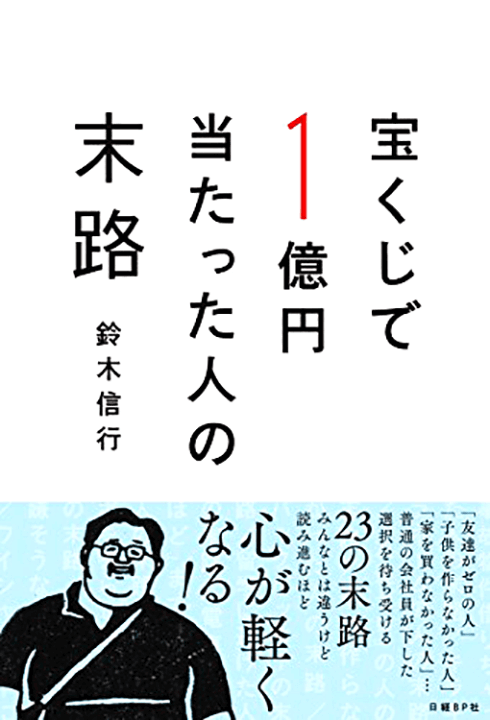 日経BP社
日経BP社