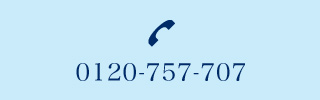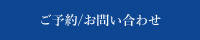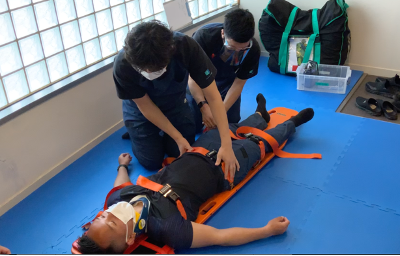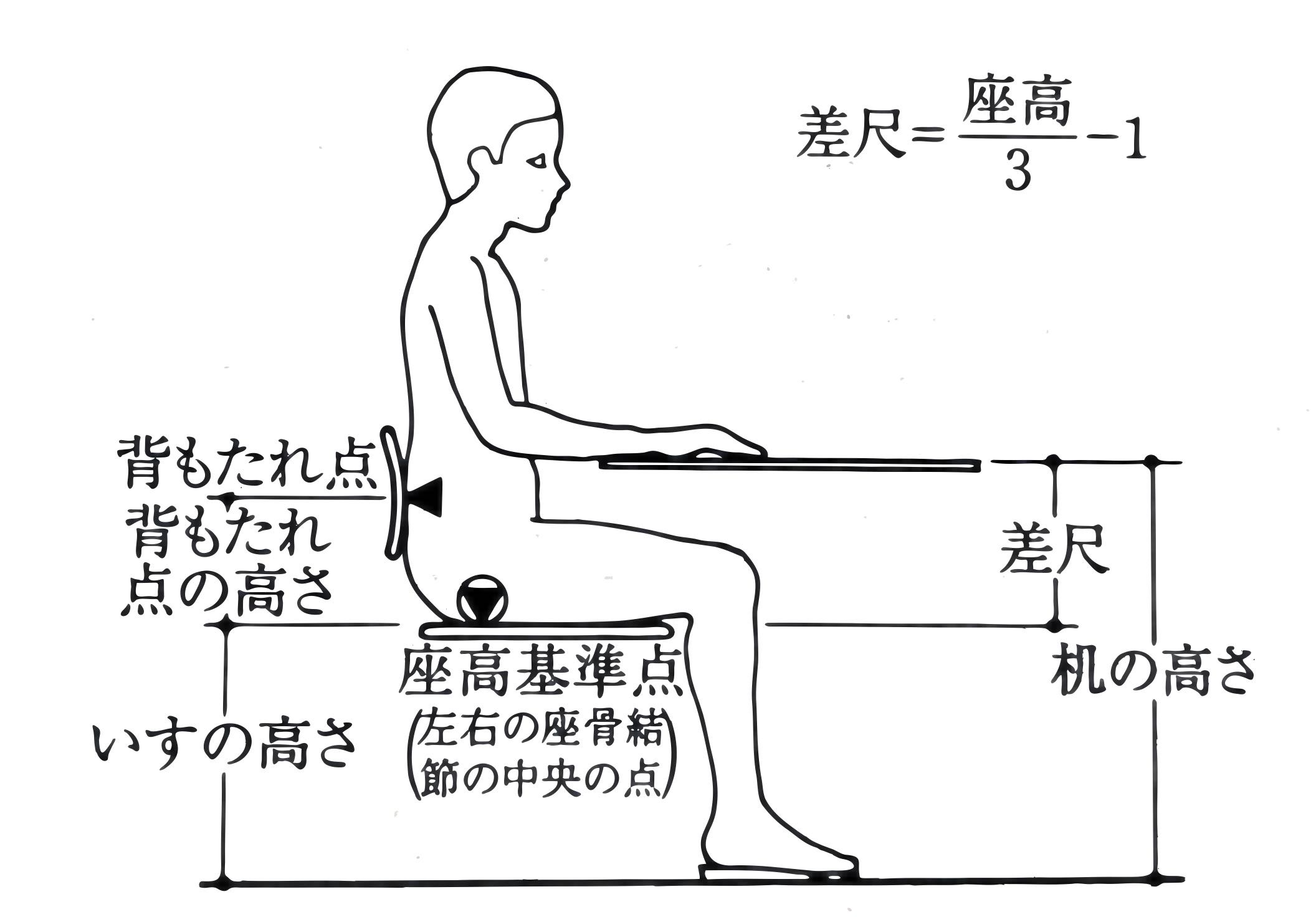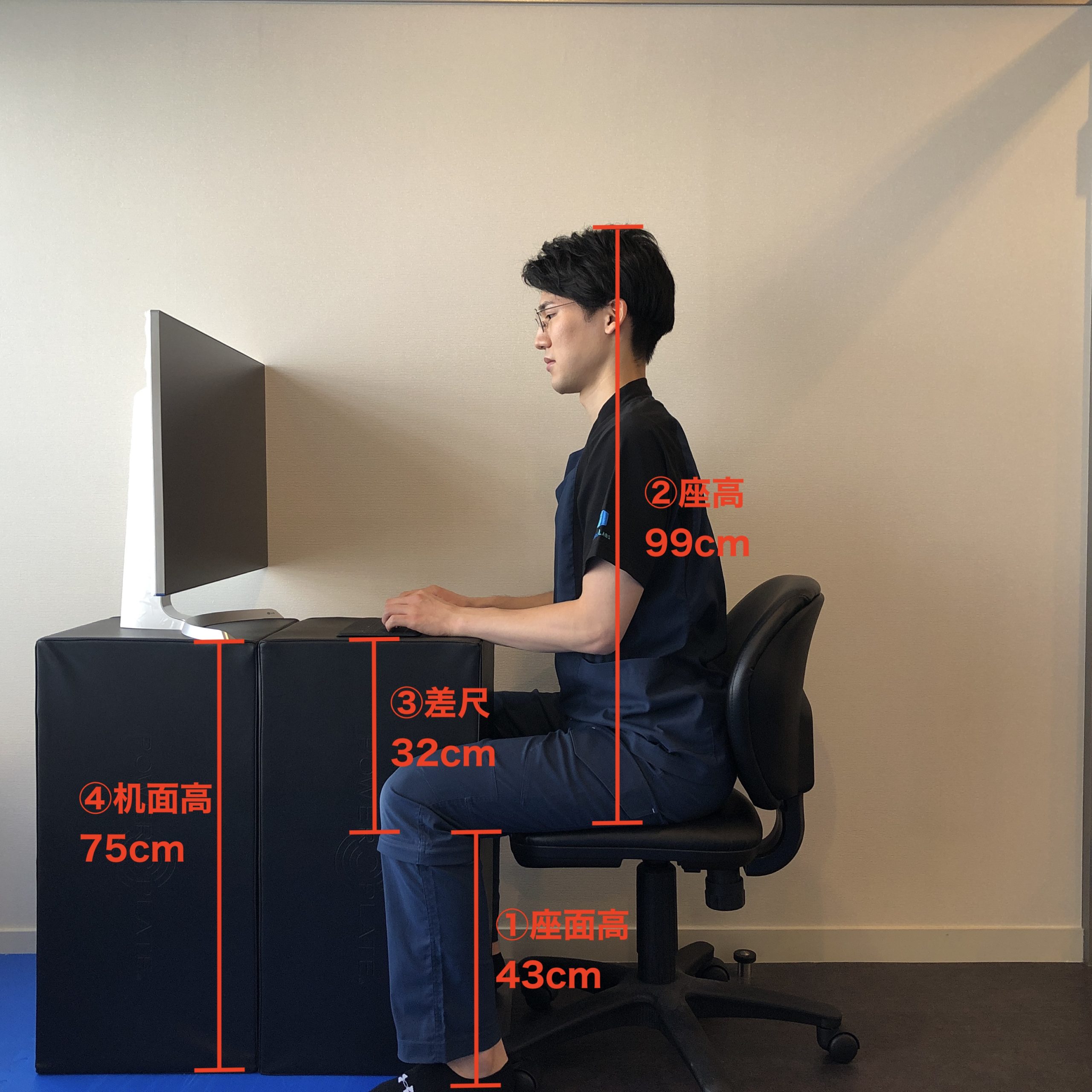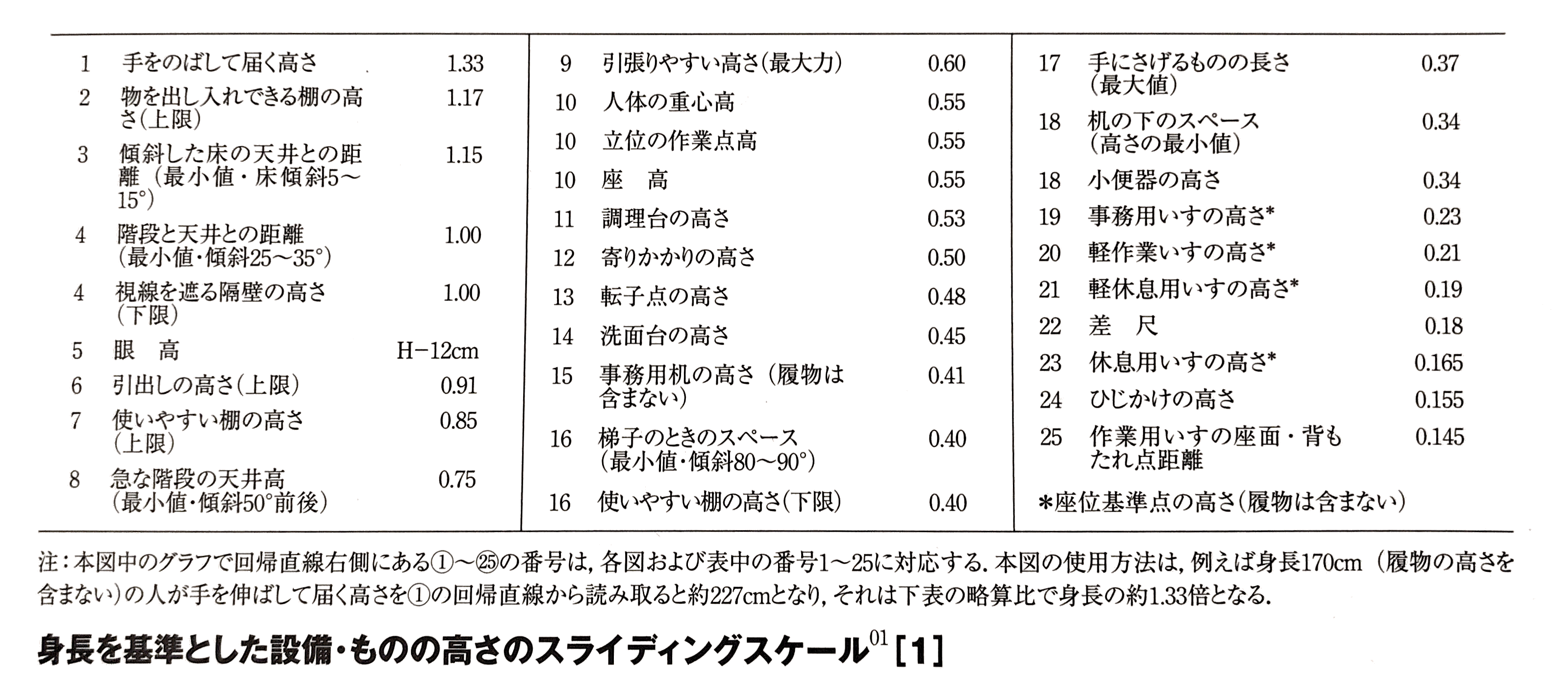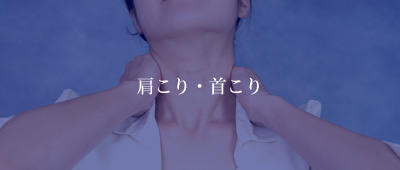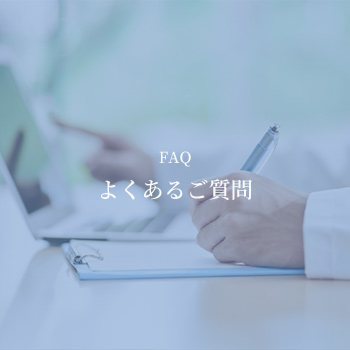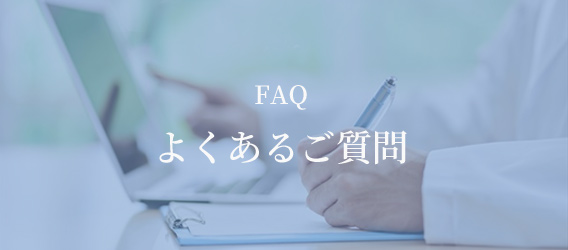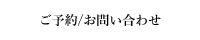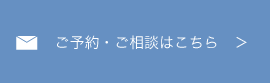はじめに
肩こりは大きく分けて、症候性肩こりと本態性肩こりの二つに分けられます。
症候性肩こりは、病気が元になって生じている肩こりで、この場合は医療機関にて病気の治療が必要となります。例えば、風邪の諸症状としての肩こり、メニエール病に伴う肩こり、肩関節周囲炎に伴う肩こり、うつ病に伴う肩こり、心臓病に伴う肩こり、などがあげられます。しばしば、テレビなどメディアで「肩こりだと思ったら怖い病気だった」などと報道されるのがこれにあたります。
一方、病気が元になって生じていないもの、言い換えれば症候性肩こり以外の肩こりを本態性肩こりといいます。本態性肩こりとは、症状は存在するけれど、現代医学的にはその原因が明らかでない肩こりのことを指します。世の中の多くの方が想像し、ご自覚される肩こりは、この本態性肩こりとなります。
本稿では、多くの方が該当する本態性肩こりの原因について解説していきます。
さて、本態性肩こりの原因は医学的に明らかとされていないのに、なぜ解説できるのかという矛盾を感じる方もいるかもしれません。
医学的に原因と言い切れるものは、因果関係が明確となった場合です。ですが、本態性肩こりを考えるうえで非常に難しいのは、ひとつの事象と症状発生の因果関係を見出すことが困難であるという点です。
筆者が考察する、本態性肩こりの原因を特定することが難しい理由は以下の4つです。
- 痛覚の閾値に個人差があるように、症状を自覚するにも個人差がある
- 症状は運動器(主に筋肉)にでるが、発症や症状の増減には自律神経や精神の影響を受ける
- 原因は想定できるが、定量化し難いため因果関係を見出すのが困難
- 複数ある原因が単一または複数絡み合うことで症状がでるが、この組み合わせに個人差がある
ご説明します。
たとえば、不良姿勢、柔軟性低下、筋力不足、運動不足などですと肩こりになりやすいイメージがあると思いますが、皆がそうであるかというとそうではありません。
おそらく皆さんの身の回りにも、姿勢が悪くても肩こりを感じない、体が硬くても肩こりを感じない、筋力がなくても肩こりを感じない、運動不足でも肩こりを感じないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
肩こりの原因を考える上で、まず一番の難しい点が、姿勢が悪い人が全員肩こりであるかというとそうではないという点です。柔軟性や筋力、運動量なども同様です。
例えばインフルエンザの原因は、インフルエンザウイルスに感染することです。これは因果関係がはっきりしていますが、本態性肩こりの場合は異なります。
症状が発生するわけですので、何らかの原因はあるはずなのですが、それでも因果関係が見出せない理由としてまずあげられるのは、痛みや凝りといった症状はあくまで主観であるという点です。
凝りも広い意味では痛みです。痛みに強い、弱いなどといわれるように、痛覚の自覚には個人差があります。貴方が痛いと感じる刺激と貴方の友人が痛いと感じる刺激は異なります。ですので、丸まった姿勢でPC作業をしていて、首肩の筋肉に負担がかかっているのは明白なのにも関わらず、症状の自覚に個人差があるのは、自覚症状の認知の仕方に個人差があるからなのです。
また、痛みの認知の仕方も、一個人のなかでも日々変動する様々な要素が関与しています。たとえば、自律神経やホルモンのバランス、精神的ストレス、気象条件 等、様々なことが関わり合い痛みの感じ方がかわってきます。
このように、医学的に因果関係がはっきりとした原因が見出せない理由として、まずは凝りという症状の定量化が難しいということと、認知の仕方が個人で異なるだけでなく、個人単位でも日々異なるという不確定要素が多分にあるからだと考えられます。
さらに、頚部の筋肉に負担をかけると考える日常生活動作、姿勢、柔軟性、筋力といった要素も、定量化がとても難しいです。
本態性肩こりは、定量化し難い様々な要素が関与しあって、症状が生じているため、医学的には原因が明らかとされていないとされているのです。
とはいえ、上記でも述べましたが、症状が発生するわけですので、何からの原因があるはずです。
ここからは、複数の文献や研究を元に、筆者の考察も交えまして、本態性肩こりの原因について解説していきます。尚、以下より本態性肩こりを「肩こり」と表記していきます。
肩こりの原因を考える上で大切なこと
はじめに、何度も繰り返しお伝えしていることですが、肩こりの原因を考える上でとても大切なことなのでここでもお話ししますね。
「凝り」はあくまでも「結果」です。
ですので、肩こりの原因は、二段階で考えると理解しやすいです。
二段階とは、
①症状を出している原因(凝り=結果の部分)
②「症状を出している原因」の原因
です。
この「結果=凝り」の部分はどういった状態になっているのか?これを結果因子といいます。
そして、この「結果=凝り」はなぜ生じるのか?これを原因因子といいます。
このように結果因子と原因因子に分けて考えることで、肩こりの原因が見えてきます。
結果因子とは
まずは①の「症状を出している原因」、結果因子から解説します。
日本整形外科学会によると、肩こりで凝り固まって症状を出す筋肉は、僧帽筋を中心に、頭半棘筋、頭板状筋、頚板状筋、肩甲挙筋、棘上筋、菱形筋が例としてあげられています。
では、首や肩が凝りでつらいという時には、これらの筋肉にいったいどういったことが起こっているのでしょうか。
この症状を出している原因(症状の元)は大きく4段階あります。
一般的に、1)から4)になるにつれて、重症度が高い状態といえますが、一個人においてもそれぞれが混在しているケースが少なくありません。
1) 代謝の異常・疲労
代表的なものは疲労や循環障害(血行不良)です。筋肉を酷使することで、その筋肉が疲労することで生じる違和感や痛みです。
また、疲労した筋肉は縮こまって硬くなるので、血流を阻害し、血行不良を招きます。血行が滞ることでも痛みや違和感が出ますが、血流が滞った状態ですと、疲労も回復しにくくなるので、症状が持続してしまいやすくなります。
ただ、筋肉疲労やそれに伴って血行不良が生じることは、生体として異常ではありません。重い荷物をもったら腕の筋肉がパンパンになって痛くなる、長い階段を登ったら脚の筋肉がパンパンになって痛くなる、ということはご経験があるかと思いますが、これは異常はことではありませんね。
このように代謝障害によって症状が出現している肩こりの場合は、休息をとったり、患部の血行を改善することで解消されます。
ですので、日々の生活の中で「肩がこったなぁ」と感じても、入浴して温めたり、良く寝たら翌日には解消されているという方は、首肩の筋肉が疲労して代謝障害を起こしている状態かもしれません。
この状態の肩こりは、セルフケアでも十分に解消や改善が可能です。肩こりでも比較的軽症なものといえます。
2) 神経生理学的な異常
スパズム(筋緊張亢進状態)
怪我をしたり、痛みがあると、人は無意識に庇ったり動かさないようにします。痛みのある箇所を庇うというのは、その部位を防御するという意味で人に本来備わっている正常な反応です。
その一環として、神経生理学な反応として「スパズム」というものがあります。スパズムとは、傷めたり、炎症が生じた箇所の周囲の筋肉が、意思とは関係なく緊張が高まり、患部を守ろうとする防御機能です。
ですので、痛みが生じたことの反応としてスパズム(筋緊張の亢進)が生じることは正常です。一旦生じたスパズムも、スパズムを引き起こした痛みや炎症が取り除かれたら、自然とスパズムも解消されるというのが正しい流れとなります。
ところが、炎症や痛みが長引くと、スパズム(筋緊張亢進)状態も長引きます。そうなると、筋緊張が高まった状態が続くわけなので、循環障害が生じ、起因となった痛みとは別に、循環障害による痛みが生じてしまいます。
こうなるとスパズムを引き起こした元々の問題が解決しても、循環障害による痛みや違和感が生じることになってしまいます。このように、スパズムは、生じること自体は患部を守り痛みを緩和するための人体に備わった正しい反応ではありますが、スパズムが長期化することで今度は痛みを出す元になってしまうのです。
「痛みが痛みを呼ぶ」という状態になって負のスパイラルに陥ってしまうのは、スパズムという反応が関係しています。
スパズムを解消するためには、まずは早期に起因となった元の痛みを緩和することが大切となります。ですので、対症療法も重要です。
また、スパズムは、筋肉に命令をする神経の興奮によって生じるので、スパズムの解消には、神経の興奮をおさえるための対処が必要です。神経の興奮をおさえるための対処として、誰でもすぐにできることは、温めたりさすったりすることです。アイシングなどの寒冷療法が効果的な場合もあります。
3) 筋膜の異常
筋肉の筋膜(Myofascia)は物理的に筋肉を保護するためでなく、筋膜内には神経が密に分布しており、感覚のレセプター(受容器)がたくさんあることがわかってきています。そのため、筋膜の異常によって、痛みやしびれ、違和感などが生じるということがわかってきています。
筋膜が異常を起こして痛みが生じるものを、筋膜性疼痛症候群(きんきんまくせい とうつうしょうこうぐん、Myofascial Pain Syndrome:MPS)と呼ばれています。
肩こりで、過緊張が起って症状を出す筋肉は、僧帽筋を中心に、頭半棘筋、頭板状筋、頚板状筋、肩甲挙筋、棘上筋、菱形筋などがありますが、これらの筋膜が異常をおこして症状が出ている場合もあります。
筋膜の異常は大きく分けて三つあります。
1, 高密度化(筋膜のシワ)
「筋膜のシワ」とよばれるものです。血行不良の状態が続くことで、筋膜への循環不全が長期化することで、筋膜の水分量が低下してしまっている状態です。構造自体がかわってしまっているわけではないので、改善のためには、患部の血行を増加させて、筋膜への水分補充をすることが必要です。
2,滑走性低下(癒着)
筋肉は筋膜で覆われていますので、隣接する筋肉は筋膜で接しています。この筋膜間には潤滑物質であるヒアルロン酸があります。不動の状態(動かさない状態)が続いたり、血行不良が続くことで、ヒアルロン酸の水分量が低下し、隣接する筋膜同士がくっついて動かなくなってしまいます。このように動きが悪い状態(滑走不全)がさらに長期化することで、癒着して完全に動かなくなっていってしまいます。動いていた箇所が動かなくなるわけですから、関節可動域や動作に変化が生じるだけでなく、循環不全にも拍車がかかります。筋膜の滑走不全を改善させるには、筋膜間のヒアルロン酸に水分を与えることが必要です。高密度化を改善させるのと同様、構造自体がかわってしまっているわけではないので、患部の血行改善が必要です。
3,線維化
筋膜に対して組織の強度を超える物理的な負担がかかると傷や炎症が生じます。傷や炎症が同様の場所に反復継続的に生じたり、大きな損傷が生じると、きちんと元通りに組織の修復が行われず、「かさぶた」のような状態で治癒が終わってしまいます。この「かさぶた」の様なものは瘢痕組織といって、筋膜とは別に組織になってしまいます。このように、線維化は、スポット的に筋膜が筋膜ではない組織になってしまうことをいいます。線維化してしまった筋膜は、血行を改善しても基本的には元にはもどりません。ですので、この筋膜の線維化は、正しくは機能的変化ではなく、下記の構造的変化に該当しますが、筋膜の異常の一環として、こちらに記載させていただきました。
筋膜について詳しくはこちらにまとめましたので併せてご一読ください。
4) 構造的変化
代謝障害や神経生理学的な異常はあくまでも機能の変化でしたので解剖学的な組織の性質や形状が変わってしまうということはありませんでした。一方、構造的変化とは、文字通り構造が変わってしまうので、異常な組織に置き換わってしまう、あるいは異常な組織ができてしまうということです。
1,モヤモヤ血管
2012年に奥野祐次医師によって発見された病態です。
慢性炎症部位・慢性疼痛部位には創傷治癒過程で生じた毛細血管が残存増殖して存在していて、この部位を血管造影で観察するモヤモヤした状態に見えることから「モヤモヤ血管」と名づけられました。モヤモヤ血管とは、異常な毛細血管の増殖です。創傷治癒の過程で毛細血管が増殖することは正常な反応なのですが、治癒が長引いたり、反復して損傷することで、本来治癒したら自然と消えるはずの増殖した毛細血管が残存してしまうのです。血管は神経とセットで存在するため、異常毛細血管に血流があるとポリモーダル受容器を刺激して疼痛が発生するというメカニズムです。
モヤモヤ血管について詳しくはこちらにまとめましたので併せてご一読ください。
2,硬結(こうけつ)
しばしば肩こりで肩の部分に触知できるシコリの部分のことを硬結といいます。
この硬結は、1843年ドイツの内科医Robert Froriep氏がリウマチ患者の筋肉中に索状に触れる圧痛部位を発見し、結合組織の沈着が原因であることを報告したことがはじまりです。その後、線維性結合組織炎、筋スパズム、酸素欠乏、炎症などの仮説が提唱されてきました。
硬結を実際に触診してみると、玉状のものだけでなく、索状だったり扁平な形状をしていることもあり、形状は様々です。
近年の病理学研究から、硬結の部位は、上記でご説明しました筋膜の線維化だけでなく、様々な変化が生じていることがわかってきました。
硬結部位は以下の状態になっています。
◆ 代謝異常
→浮腫、エネルギー供給と酸素流入の低下、pH低下
◆炎症反応
→肥満細胞増加(ヒスタミン放出)、血小板増加(セロトニン放出)
◆細胞の変性
→核の増加、ミトコンドリアの異常(赤色ぼろ線維=Regged Red Fiber)、筋原線維の異常(虫食い線維=Moth-Eaten Fiber=収縮フィラメントの溶解とZバンドの破壊)、プロテオグリカン増殖
硬結ができる機序はこのように考えられています。
筋損傷・過剰な筋疲労 → 細胞膜・筋小胞体の破壊
↓
カルシウムイオンの過剰流入 → 局所的な筋収縮亢進
↓
筋弛緩のためにATPが必要となり代謝が亢進するが、過剰な筋収縮が局所循環障害を招き酸素欠乏とエネルギー不足を招く
↓
筋収縮状態が恒常的となる
硬結部位は、代謝異常と炎症反応という機能上の変化だけでなく、筋細胞自体の構造が変化してしまっているのです。つまり、硬結は、いくら温めたり、ストレッチや揉みほぐしを行っても、解消はされないのです。
ですので、硬結の状態になってしまっている場合、代謝異常という機能上に問題だけでなく、細胞自体が変化してしまっているため、組織を破壊し、再生(リモデリング)を促す対処が必要となります。
肩こり・首こりの根本的な改善には結果因子だけでなく原因因子を考えることが大切
さて、ここまでは凝りの症状を生む元(結果因子)、つまり凝り固まってしまっている筋肉そのものにどのような変化が生じてしまっているかについて解説しました。
「こり」を感じているところ(筋肉)をほぐせば、一時的に解消はされますように、結果因子に対して対処を行えば、ひとまず症状は解消します。これを対症療法といいます。
たとえば、普通の本態性肩こりならば、僧帽筋の部分がつらいと感じるならば、僧帽筋をほぐせばラクになります。
ところが、みなさん誰もがご存知のとおり、ほとんどの場合は時間の経過と共に再び症状が生じてきます。また、凝る→ほぐす→凝るの繰り返しによって、慢性化していってもしまいます。
「凝ったらほぐす」を繰り返さないためには、そもそもなぜ凝るのか?を知る必要があります。慢性的な肩こりを治すためには、まず原因を知る、その原因を解決できれば根本的な改善につながります。
次に、結果である「凝り」がなぜ生じるのかの部分、原因因子について解説します。原因因子とは、上記でご説明した結果因子の原因です。
肩こりの原因因子は、様々ありますが、上記でご説明してきた結果因子が生じさせるのは、首や肩の筋肉・筋膜に反復継続的な物理的な負荷が加わることです。
これに加えて、環境や何らかの刺激により自律神経のバランスや精神が乱れることで過緊張が生じたり、痛みを感じやすくなることで、症状を自覚するようになります。
次回は、肩こりの根本原因(原因因子)について解説します。
参考文献
TOPに戻る>> 肩こりや首こりの治療や解消なら専門情報サイト肩こりラボ

執筆者:丸山 太地
Taichi Maruyama
日本大学文理学部
体育学科卒業 東京医療専門学校 鍼灸マッサージ科卒業
上海中医薬大学医学部 解剖学実習履修
日本大学医学部/千葉大学医学部 解剖学実習履修
鍼師/灸師/按摩マッサージ指圧師
厚生労働省認定 臨床実習指導者
中学高校保健体育教員免許
病院で「異常がない」といわれても「痛み」や「不調」にお悩みの方は少なくありません。
何事にも理由があります。
「なぜ」をひとつひとつ掘り下げて、探り、慢性的な痛み・不調からの解放、そして負のスパイラルから脱するためのお手伝いができたらと考えております。